子育てに悩みは尽きませんが、お子さんがたくさん食べ過ぎてしまうことで悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
うちの子も、離乳食時期はほとんど食べなかったのですが、1歳6ヶ月で断乳した途端に、別人のようにバクバクと食べ始め、親のこちらの方が戸惑ってしまいました。
毎食、今までの2倍以上食べて、さらにおやつまで欲しがるようになり、びっくりしたのと同時に、どこまで与えれば良いのか分からなくて、悩んでしまう事もありました。
そこで今回は、お子さんの食べ過ぎで、将来肥満になってしまうのではないかと不安に感じている方に、
食べ過ぎてしまう原因はどういったことがあるのかについてと、食生活の改善をする時には、どのようにすればいいのかについてお話していきたいと思います。
食べ過ぎる原因を考える
小さい子供に、いくら「太るから食べるのやめなさい!!」と言っても、子供が小さいうちは、なんで怒られているのか意味が伝わりにくいですよね。
さらに食べたい気持ちを無理やりに押さえつけられてしまうので、子供は嫌がったり、余計に食べたがったりしてしまう可能性もあります。
無理に食べさせないようにする前に、まずは、お子さんがたくさん食べてしまう原因は何なのかについて考えてみる事をおススメします。
ここからは、お子さんが食べ過ぎてしまう原因はどのようなことが考えられるのかと、
そのような場合には、どのように対処していけばいいのかについてお話していきたいと思います。
<グズると何かしらあげてしまう>
乳幼児期に完全母乳だった方は、「おっぱいはいくら飲ませても大丈夫」と言われる事も多く、子供が泣けばおっぱいをあげていた、という方も多いのではないでしょうか。これが、断乳した後にでも続いてしまうと、泣いたりぐずったりしたら、おやつやご飯をあげる…という事が習慣になってしまうことがあります。
食欲旺盛なお子さんであると、グズっては何かをもらって食べて、さらにおやつも食べて、ご飯も食べて…と、与えられたら与えられた分だけどんどん食べてしまうことが考えられます。
また、ご飯以外に、おやつやスナック菓子などを食べ過ぎてしまうことが続くと、肥満や内臓に対する負担も気になってしまいます。
私の友人でも、子供が食欲旺盛な子がいます。
その子は、離乳食が始まってから離乳食もたくさん食べた上に、子供が泣けばおっぱいをあげ、さらに一日に何度かはミルクもあげていました。
生後間もなくで会ってから、9か月位になって久しぶりに会った時には、見るからに大きくなっていてビックリしたのですが、
その時一緒にいた、先輩ママさんの友達が
「これはちょっと太ってきてるし、ご飯あげ過ぎだから、ちゃんと見直した方がいいよ!」
と、その友達に言っていました。
その後、病院でも子供が「肥満」になってしまっていると、注意を受けたようで、ミルクをあげるのはやめて、離乳食の量も減らしたそうで、
次にその子に会った時には、だいぶスッとしていて肥満範囲ではなくなったと話していました。
対策
食欲旺盛の子は、離乳食が始まると、最初のうちからあまり抵抗なく食べてくれる子が多いようです。始めてのお子さんであると、親としては「食べてくれるかな…?」と不安な気持ちをもって離乳食を開始しますから、
パクパク食べてくれると、安心しますし、うれしい気持ちもあってどんどんあげてしまいたくなる気持ちもあるでしょう。
ですが、離乳食はあくまでも食事する事になれる為の期間でありますから、そこまでたくさんの量を食べさせる必要はないようです。
ミルクや母乳を主体に考えて、お子さんがどんなにたくさん食べたがっても、離乳食の量は、育児本や栄養士さんが勧める月齢に合った量を与えるようにするといいでしょう。
また、離乳食時期のお子さんよりも難しいのが、離乳食時期を終えた幼児に、グズった時に何かおやつなどを与えて泣き止ましているというお子さんです。
泣くと何かしら食べ物を与えて泣き止ませていた、という親御さんは、初めはどのようにあやしたらいいのか分からず、戸惑ってしまうかもしれません。
確かに、何かを口に入れると一時的には静かになりますが、これを繰り返してしまうと、お子さんは「泣けば何かをもらえる」と思ってしまう可能性があります。
まずは、お子さんが泣いても、少しくらいならほっておく位の気持ちを持っても良いでしょう。
お子さんも、分からないようでいて実はちゃんと大人がやる事や、言葉を理解しています。
ほっておくと、意外と何分かすると泣き止むことも多いのです。
泣き止んだら、抱っこして外を見せたり、絵本を読んであげたり…などお子さんの気持ちが切り替えられるようにしてみましょう。
外出時や電車の中など、どうしても静かにしていてもらいたいという時には、たまにであればお菓子ような物を与えてもいいのではないでしょうか。
そして、あげる時には「これだけだよ」とか、最初にお子さんと約束をしてから与えるようにすると良いでしょう。
うちの子も、おやつなどを急に取り上げられるととても嫌がりますが、「これで最後だよ」と念を押してから与えると、
気持ちの切り替えができるのか、ちゃんと終わりにする事が出来るようになりました。
また、何かを食べないとどうしてもグズってしまうお子さんには、与えるおやつをおにぎりやお芋など、
捕食としても大丈夫な物にする事で、大人も安心して与えることが出来るようになりますからおススメです。
<お腹が空きすぎてしまう>
乳幼児期のお子さんは、小さい体にどこからこんな体力があるの?と思う位に、走り回ったり、動いてない時はない位に動き回りますよね。そうすると、もちろんその分体のエネルギーが消費されますから、お腹が空いてしまいます。
特に活発に動き回る子は、多くのエネルギーを消費してしまいます。
ですから、食べても食べてもすぐにお腹が空いてしまうので、結果たくさん食べるという事になってしまいます。
対策
エネルギー消費してお腹が空くのは仕方のない事ですから、その分を摂取しても問題はありません。ただ、ここでスナック菓子やアイスなどをたくさん食べてしまうと、塩分や糖分、添加物を体にたくさん取り入れてしまうことになります。
やはり、捕食として考えて、おにぎりやサンドイッチ、フルーツなどを与えるようすると良いでしょう。
また、お菓子と呼ばれる物ばかりを食べていると、ご飯よりもお菓子の方が美味しく感じてしまう子も多いようです。
ご飯はそんなに食べないのに、お菓子はパクパク食べて「もっと!」と欲しがる…なんてお子さんは、お菓子の量を制限することが大切になってきますね。
お菓子は、週末のお楽しみにするとか、一日にこれだけとルールを決めるのも良いでしょう。
毎日食べるよりも、たまに食べる方がより一層美味しく感じるのは、大人もお子さんも同じ事だと思いますよ。
うちの子も、たくさん食べるようになった時に栄養士さんに相談したところ、「便通もよくて、急激に体重が増えることが無ければ、どんどん食べさせていいのよ」と言われてビックリしました。
でも、「お菓子ではなくおにぎりにしてね、おにぎりならいくら食べても大丈夫よ」と言われました。
子供は、食べても動き回って、どんどん消費してしまうのでとっても燃費が悪いのだそうです。
そのエネルギー源を補充するには、おにぎりが一番だとその栄養士さんはお話されていました。
<家で過ごす時間が長い>
大人もそうですが、家にずっといると手持ち無沙汰になって、何となくおやつをつまんだりしてしまいますよね。それと同じように、お子さんも家のなかばかりで過ごしていると、おやつを食べたがることが多くなる傾向があります。
1歳を過ぎてくると、段々と知恵をつけてくるので、親の行動を見て「ここに美味しい物がある!」という事を理解するようになってきます。
そうすると、自分でおやつのあるところまで言って指さしたり、もらえないと分かるとグズってもらえるまで欲しがったりすることもあります。
対策
家の中で過ごす時間が長いなと感じる場合には、出来るだけ日中は外に出る事をおススメします。外に出ると言っても、まだよちよち歩きのお子さんの場合や、雨の日などは、無理して「外遊び」をする必要はありません。
ですが、親の買い物につき合わせるよりは、できるなら子育て支援センターや児童館などに行って、室内であってもお子さんが身体を動かして遊べるようなところに行く事をおススメします。
子供は、好きな遊びに夢中になると、大抵の場合はおやつの事など忘れて遊んでくれるようになります。
食生活を見直してみよう
これまでは、食べ過ぎてしまう原因はどのような事があるのかについてお話してきましたが、
「そうは言っても、うちの子は原因もなく、いつでもおやつを欲しがるし、おやつを食べてもご飯もたくさん食べるから悩んでるんです」
と、思われる親御さんもいらっしゃるかもしれませんね。
確かに、元々「食べる事」が好きなお子さんはいらっしゃいます。
「食べること」は、身体の成長には欠かせない事ですし、たくさん食べる子は風邪をひきにくいお子さんはも多いと言われています。
ですから、極端に太ってしまっているとか、どこか遊びに行っても遊びには全く興味を示さないとか、常に何となく元気がなさそう、などといった病気が心配になるような事も無く、
元気に走り回って、遊んでいるようならば、多少体が大きくてもそれほど心配する必要はないでしょう。
ご飯も、本人が食べたがる分だけ食べさせても、成長と共に身長も伸びていくので、そこまで問題になる事は無いことがほとんどです。
ですが、食事の内容には気を配る必要はあるでしょう。
先ほどからお話しているように、ご飯もしっかりと食べるからと言って、おやつにスナック菓子やジュースのような物ばかり与えてしまうのは、
大きくなった時に、肥満や糖尿病といった生活習慣病になってしまう可能性が高まってしまいます。
おやつも捕食として考えて、おにぎりやフルーツなど、ご飯の代わりとなるような物をあげるようにしましょう。
お子さんに与える食事は、成長に必要とされるタンパク質やカルシウム、ミネラルやビタミンなどがバランス良くとれるように心がけるようにすると良いでしょう。
栄養相談での栄養士さんのお話で、こんな事をお話されていました。
1回の食事量の目安としては、
主食(ご飯、パン)は、お子さんの両手で受け皿を作って、そこにおさまる位
主菜(お肉、お魚、卵)は、お子さんの握りこぶし1個位
副菜(野菜)も、お子さんの握りこぶし1個位
なのだそうです。
おやつに、ご飯で取り切れなかった乳製品(牛乳、チーズ、ヨーグルトなど)やビタミン(フルーツ)などを与えるといい、という事でした。
これは、大人になってからの食事量の目安にもなるというお話だったので、参考になるなーと思いました。
もしも、おかわりをするようなら、お子さんはエネルギー使うので、おかずばかり食べるよりも主食を食べた方が良いそうです。
食欲が旺盛なお子さんは、食べるのが早い子も多いとよく耳にします。
大人でもそうなのですが、あまりよく噛まずに食事をしてしまうと「満腹感」を、なかなか感じる事が出来なくなってしまいます。
そういったお子さんには、食事の中に、よく噛んで食べらるような物を出してあげるのも良いでしょう。
例えば、いつもよりも野菜を大きく切ってみたり、おやつには小魚を出してみたりするのも良いですね。
また、食事をしている時にお子さんとの会話を増やすと、自然と食べる速度がゆっくりになるので、早食い防止に役立ちますし、
食事の時間が、ますます楽しくなりそうですよね。
まとめ
いかがでしたか?
親としては、お子さんが食べ過ぎてしまっても心配になりますが、逆に全然食べてくれなくても心配になってしまいますよね。
そのうちに、幼稚園や保育園に行くようになると、いつも食べてばかりとはいきませんので、集団生活の中で我慢する事も自然と学んでいきます。
また、色々な遊びを通じて、食べる事以外にも好きな事が増えてく事でしょう。
そうすると、自然といつも何かを食べたがるという事が減っていくことがほとんどです。
たくさん食べても、お子さんが元気いっぱいであるのなら、多少体は大きくても、おおらかな気持ちで見守っていく気持ちを持つ事も大切ですね。







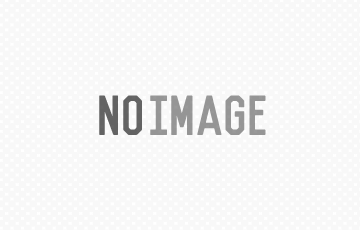



コメントを残す