子育ての中でも、大変な時期に挙げられている「イヤイヤ期」は、
早いお子さんですと1歳半位から始まり、多くのお子さんが2歳前後でイヤイヤのピークを迎えます。
また、「うちの子はイヤイヤ期がなかったな」と思っていたら、4歳位になってイヤイヤが始まった、なんてお子さんもいらっしゃいます。
イヤイヤ期は、お子さんの自我の芽生えの時期と言われ、身の回りのお世話を全て周りの人にやってもらっていた時期を過ぎ、
色々なことに興味を持ち、何でも「自分でやりたい!」という気持ちが出てくる時期です。
イヤイヤ期になるという事は、お子さんの心が順調に発達しているという証拠ですので本来ならば喜ぶべき出来事です。
ですが、今までとは別人のように、ちょっとしたことで癇癪を起して泣き出したり、
一度「イヤイヤ」が始めると、なだめたりおだてたりしても、なかなかイヤイヤが治まらないということが続くと、
親としても段々疲弊して、イライラしてしまったり、どのように対応したらいいのか分からずに、困ってしまいますよね。
そこで今回は、年齢別でどのようなイヤイヤの特徴があるのかについてと、
その「イヤイヤ」に対する対処法をご紹介していきたいと思います。
1歳半頃のイヤイヤ期

<特徴>
1歳半位になると、多くのお子さんが二本足で歩けるようになり、離乳食から幼児食に変わっていく時期であります。早いお子さんですと、今までは周りの人にやってもらっていた事を少しずつ「自分でやってみたい」という気持ちが出てきます。
ですが、まだまだ言葉は未熟ですので、「やってみたい」という自分の気持ちを、上手く相手に伝える事が出来ません。
そんな時に、今まで通りに周りの人がやってあげようとすると、「イヤイヤ」をして抵抗するようになります。
この時期は、「イヤ」という単語自体を言えないお子さんも多いので、自分が「それは嫌」と思うと、
物を投げたり、相手をギュッとつねったり、泣いたりして自分の気持ちを訴える事もあります。
今までは何の抵抗もなくやってもらっていた事を、いきなり嫌がったり、やりたがることもあります。
例えばおむつを履くのを嫌がったり、ご飯を口に入れられる事を嫌がったり、お風呂を嫌がったり…などお子さんによって様々…
また、離乳食は順調に進んでいたのに、1歳半位で、急にご飯の時間を嫌がるようになり、スプーンを投げたり、お皿をひっくり返したりするようになることもあるようです。
イヤイヤはある日急に始まる事が多いので、親も最初は「イヤイヤ期」なのかも分からず、「なんでイヤイヤするの?」と思う事から始まる事が多いです。
ですが、それがイヤイヤ期のイヤイヤですと、同じようなイヤイヤが、そのあと続いていくので、何回目かで「イヤイヤ期なのかも…」と気付き始めます。
では、1歳半位のイヤイヤ期はどのように対策していけばいいのでしょうか?
<対策>

1歳半の子供は自分が話す言葉は未熟であっても、親の話している事はある程度は理解しています。
やりたいことがある時や、かまってほしい時に、親の都合(今は時間がないとか、今は忙しいなど…)
だけで「ダメ!」と言って突っぱねてしまうと、子供は自分の気持ちを受け入れてもらえなかったことに対して抵抗します。
大抵の場合、「こんな忙しい時間になんで…」という時や、「こんなに人がいっぱいいるところでなんで…」という時にイヤイヤが始まります。
親からしてみると、「もう!!」と、イライラした気持ちになってしまいますが、
そんな時は、その場はとりあえず、その子の気持ちを優先してあげてやらしてあげたり、かまってあげるようにしてみると良いでしょう。
そして気持ちが少し落ち着いたら、「今日は時間が無いから、これでおしまいね」などと、できない理由を子供に説明してみましょう。
また、1歳半位ですと、そのことに執着した気持ちがあってイヤイヤをしている訳ではない事もあります。
ですから、「気持ちを他の事にそらせる」ようにする事も効果的です。
ぐずったら外やベランダに出てみたり、何か音の出るおもちゃを見せてみたりすると、
気持ちが一瞬そちらに向いて、イヤイヤしていた事を忘れることもあります。
もちろん、お友達を叩いてしまったり、物を投げてしまったりという、相手や自分にとって身の危険があるような行為をしてしまった時には、キチンと注意する必要があります。
そんな時には、ダラダラと怒ったり怒鳴ったりはせずに、「ダメ!」や「いけない!」など、短い言葉で少し低めの声で、子供に分かりやすいように叱ります。
その後、「~したかったね」など、その子の気持ちに寄り添った言葉を付け加えてあげると、
ちゃんと自分の気持ちを分かってくれてるんだと、子供に伝える事ができるので良いでしょう。
すぐには、その行動が無くならなくても、繰り返して「これは危険だ」という事を伝え続ける事で、段々と理解していくようになります。
2歳のイヤイヤ期

<特徴>
2歳になってくると、「自分でやりたい!」という気持ちが更に大きくなり、自分のやりたくない事をやる事への抵抗も大きくなっていきます。「魔の2歳児」と言われるように、多くのお子さんがイヤイヤ期に差し掛かる時期でもあります。
自分で出来る事も増えてきて、色々な事をするのが楽しい時期でもあります。
「こうしてはいけない」という感情がまだほとんど無いので、自分の感情のままに自由に行動します。
食事の時、遊びの時、朝やお昼寝の寝起きの時、出かけ先であっても、とにかく所かまわずに「イヤイヤ」をする事があります。
よく、デパートなどで、床に仰向けになって泣きながら「イヤイヤ」をしている子を見かけることがありますが、
それも、イヤイヤ期のお子さんの特徴とも言える傾向でしょう。
例え叱られたとしても、「どんな行動がいけないのか」という事を、まだあまり理解出来ない時期なので、同じことを何度も繰り返してしまいます。
ですから、「この間叱ったのに、またやってる…」という事が何度も起こりますので、
親の方もウンザリしてしまう方もいらっしゃるでしょう。
では、2歳のイヤイヤ期にはどのように対策をすればいいのでしょうか?
<対策>

「イヤイヤ」している事が、相手や自分にとって危害のある危険な行動なのか、それとも、危険ではないけれどわがままに思える行動なのかを判断しましょう。
先ほどもお話したように、相手や自分にとって危険な行動の場合には、即座に「それはやってはいけない」という事を伝える必要があります。
ですが、危険な行動ではないけれど、一見わがままに見える「イヤイヤ」は、その子の何かしらの「気持ちの現れ」であることを理解する必要があります。
家事をしていると、いつも何かしら邪魔してくる子も多いでしょう。
また、買い物に行ってもカートを押したがったり、買い物をかごを持ちたがる子もいるでしょう。
親としてはなかなか家事や買い物が進まず、段々とイライラしてきてしまいますよね。
そこで子供に、「やめて!邪魔しないで」というと、「いやー!」と泣く…。
あやしている時間もないので、そのままほっておくと、より激しく泣き叫ぶ…さらにイライラして「じゃあ、勝手にしなさい!」となってしまいそうですよね。
ですが、多くの場合で、子供は親の邪魔をしたいのではなく、「お手伝いをして褒められたい」という気持ちであったり、
「親と同じことをしたい」という気持ちだけで、その行為をしているということを理解してあげて欲しいのです。
ですから、たとえ「邪魔だな」と思っても、危険ではない程度であるのならば、
親と同じ事をさせてあげたり、似たような事を出来る物を与えてあげたりすると、意外と大人しくその邪魔な行為をやめてくれる事もあるのです。
例えば、キッチンに立っている時に邪魔してくる場合には、危なくないキッチン道具を貸してあげて、「何か作ってー」と言うと、喜んで作る真似をして遊んだり、
洗濯物をたたむ時に邪魔をしてくるようなら、「これをたたんで」と言って、タオルを差し出したりすると、タオルで畳む真似をして遊んだりしてくれます。
「どうせ出来ないんだから」と、初めからやらせないのではなく、できなくてもとりあえずはやらせてあげるようにすることで、
子供との信頼関係を築いていくことができるようになります。
また、もう帰らなくてはいけない時間なのに遊びに夢中になっていて「帰るよ」というと「いやー」というイヤイヤや、
子供が遊んでいるおもちゃで、他の子が遊びたがっていたので「順番ね」といって他の子に貸してあげるように言うと、まだ遊びたがって「いやー!」というイヤイヤ。
無理矢理にベビーカーに乗せたりすると、のけぞって嫌がったり、他のおもちゃで遊ばせようとしても、さらに嫌がる…。
そのイヤイヤを受け入れると、わがままになってしまうのではないかと思って、きつく「ダメって言ったでしょ!」と言ってしまいそうになりますよね。
ですが、この時期の子供は自分の気持ちを「受け入れてもらえないこと」で、自分の事を否定された気持ちになってしまう事があるのです。
そうなってしまうと、親子の信頼関係が上手く築いていくことが出来ずにさらにイヤイヤが続いてしまう可能性があります。
そんな時には、頭ごなしにダメというのではなくて、なぜダメなのかということを説明してあげるようにしてみて下さい。
また、時間がある時には一旦はイヤイヤを受け入れて見守ってみるという方法も効果的です。
帰ろうとした時に嫌がるのなら、「じゃあ、あと何分ね」と言って少しだけ待ってみる。
オムツをするのを嫌がるのなら、少しの間そのままオムツ無しで過ごさせる。
そうすると、子供の気持ちも落ち着いて意外とすんなり帰ったり、おむつを履いてくれたりします。
イヤイヤ期がピークの時には、ママだけで育児を頑張ったりせずに、パパやおじいちゃんおばあちゃんの手を借りたり、
一時保育を利用してみたり…とできる範囲で、ママの方もリフレッシュするようにできると、
子供のイヤイヤを大きな気持ちで受け止める事ができるようになりますよ。
3歳のイヤイヤ期

3歳となると、ほとんどの子が言葉を話せるようになるので、親と言葉でのコミュニケーションを取れるようになります。
言葉の発達と共に自分の気持ちを伝えられるようになって、イヤイヤ期のピークを過ぎる子も多いですが、まだまだイヤイヤ期が続くこともあります。
3歳のイヤイヤは、自分の気持ちを受け入れてもらえない事のイヤイヤが多く見られます。
親としては、言葉も話せるようになって、自分の身の回りの事がほとんど出来るようになってくると、
一人の人間として子供を見るようになっていきます。
そうすると、子供に対しての気持ちも「出来ないから仕方ない」という気持ちから、
「ダメな事はわかるでしょ?」とか「言わなくてもできるでしょ?」という気持ちに変わっていきます。
ですが、3歳の子供は、出来ることが多くなったとはいえ、自分で何でもできる訳ではありませんし、まだまだ親に甘えたい盛りです。
そして、そんな気持ちを上手に表現できる子はほとんどいません。
そんな親との気持ちの違いのもどかしさから、せっかく出来るようになったことであっても「いやー!」と言ってやらなくなったり、
親に対して「嫌い!」となどと、本当の気持ちとは逆のことを言ってしまう事があるのです。
また、言葉の発達や頭の発達は著しく、親の行動を見ていて叱った事に対して「ママだってやってるじゃん」と屁理屈を言って来たり、
言葉だけのイヤイヤではなく、家での居心地が良くないと感じると、家ではご飯を食べなくなってしまったりする行動のイヤイヤをすることもあります。
こうなってくると、親の方も「可愛くない!」なんて思ってしまったりして、
子供相手にムキになって言い争いをしてしまう…なんてケースも少なからずあるのです。
では、3歳のイヤイヤ期はどのように対策すれば良いのでしょうか?
<対処法>

3歳のイヤイヤ期は、コミュニケーションをとる事で解決していきたいですね。
嫌な理由は何なのかを子供に聞いてみましょう。
「どうして嫌なの?」「なんで嫌いなの?」などと、子供の気持ちを聞き出してあげるように聞いてみましょう。
子供が上手に答えられない場合には、「~だったから嫌だったの?」「寂しかったから~しちゃったの?」などと、
子供の気持ちを察してあげる質問をしてあげると、子供も自分の気持ちを分かってくれようとしていると感じる事ができ安心して、正直な気持ちを伝える事が出来るようになっていきます。
また、子供が暴力を奮ってしまった時には、厳しく「ダメ!」と抑制するだけではなく、
「あなたがそういう事をすると、ママは悲しい」と言う方が、子供に「これをしてはいけないんだ」ということが伝わりやすいこともあります。
子供が、泣きじゃくって話もできない時には、抱きしめたり、「大好きだよ」と伝える事も良いでしょう。
この時期のイヤイヤは、親の愛情に対する不安な気持ちからイヤイヤをする事も多いのです。
スキンシップを増やして、子供に愛情を伝えるようにしてみましょう。
また、「これは出来て当たり前」という気持ちは一旦無くして、今まで普通にできていた事であっても、出来たら褒めてあげる事も効果的です。
靴を履けたら「できたね!」、ご飯を全部食べたら「すごいね!」と言ってみましょう。
そういったことを繰り返すことで、子供は自分が認められていると感じる事ができ、自分に自信を持つことが出来るようになってイヤイヤも減っていくでしょう。
4歳のイヤイヤ期

4歳となると、イヤイヤ期とは言っても一種の反抗期になります。
自分以外の事にも興味をもつようになり、親が言ったことに対して「なんで?」「どうして?」と疑問に思ったり、
何か珍しい物があったら「見て!」と言って、親との共感をもちたがったりします。
もちろん、時間がある時には親の方も子供と向き合って、質問に答えたり、一緒に共感する事も出来ますが、
子供の興味は、一度だけで終わることありません。
何度も何度も同じようなことを、「なんで?どうして?見てみて!」と繰り返されると、
親の方も心に余裕がない時には、「今は待って!!」「うるさい!」となってしまうこともあります。
ですが、子供は親の状況を判断することはできません。
親に冷たくされることが続くと、自分の欲求が通らない事への悲しみでいっぱいになってしまい、物に当たってしまったり、へそを曲げてしまったりすることもあります。
また、幼稚園や保育園でのお友達同士での会話も増え、言葉も「いや」だけではなく、
「うるせー!」と言ったり「ばばあ!」と言ったり…どこでそんな言葉を覚えてきたの?ということを言うようになったりします。
親の方も、子供のそんな言葉をそのまま受け取ってしまって、辛い気持ちになってしまう事もあるでしょう。
口も達者になってきますので、「~して」というと「今やろうとしてたの!」などと生意気なことを言ったり、
体力も身体も成長していますので、反抗して泣いたり暴れたりしてしまうと、親も全身で受け止めないと対応できなくなったりします。
そうなってくると、心も体も体力勝負と言った具合になってしまいますね。
さらに、色んな事ができるようになったからこそ、自分が出来ない事に対するイライラが反抗となって現れることもあります。
では、4歳のイヤイヤ期はどのように対処していけば良いのでしょうか?
<対処法>

特に男の子に多く見られる「汚い言葉遣い」ですが、これは言った時の相手の反応を見て楽しんでいたり、
言葉の意味よりも、響きを楽しんでいることが多いようです。
ですので、言葉使いに対して過敏に反応すると、その反応に喜んで余計にその言葉を使ってしまう事が考えられます。
それよりも、冷静に「その言葉カッコよくないよ」とか「あまり好きじゃないな」と伝える方が子供には伝わりやすいでしょう。
女の子は、逆に変に大人ぶった生意気なことを言うようになっていきます。
それは、親が自分の気持ちを理解してくれない悲しみのから発されることが多いので、
「なんでそんなことを言うの?」と本当の気持ちを聞くようにしてあげる事で、落ち着いてくることが考えられます。
また、自分のペースでやりたいという気持ちが芽生えてくる時期でもありますから、
もどかしくても、子供のやりたいようにやらせてみることもイヤイヤを阻止するには効果的です。
失敗するからといって、親がなんでもやってしまうと、子供は最初は反発しますが、
そのうち「どうせやらせてもらえない」と諦めるようになっていき、最終的には自分に自信が持てずにやる前から出来ないと思う子供になってしまうこともあります。
失敗する事が分かっていても、危険ではない範囲ならば、子供の意欲を尊重して、やらせてあげる勇気を親が持つことも必要でしょう。
色んな事に興味をもっている時期は、人生の中でもとっても貴重な時期ですから、親の方もできるだけ子供の好奇心をつぶさないようにしたいですね。
大きな気持ちで、なんで?どうして?見てみて!という子供の気持ちに応えられるようにしていきたいですね。
あまり予定を詰め込まないようにして、時間に余裕を持って接することが出来ると、親子の関係も良好になっていくのではないでしょうか。
まとめ
いかがでしたか?
イヤイヤ期でとてつもない癇癪があったりすると、「親の育て方が悪かったのかな?」という不安も出てきてしまう事でしょう。
ですが、イヤイヤ期は心の順調な成長の証です。
親が悪い訳では決してありません。
毎日毎日、子供の気持ちに寄り添い、子供に愛情を伝えてあげることが出来ていれば、必ず乗り越えていく日がやってきます。
頑張って育児をしていることに誇りをもって、周りの目は気にしないようにして、イヤイヤ期を乗り越えていきましょう!!





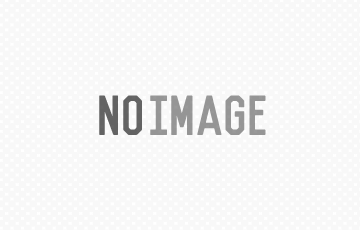





コメントを残す